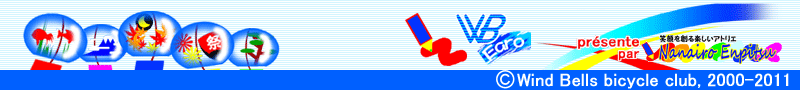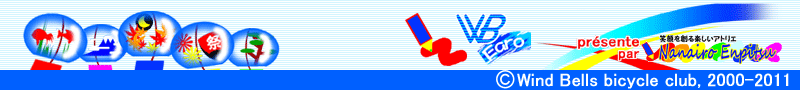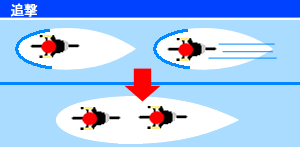
アタックした選手から引き離されまいと追いかけたり、あるいは前方に走行車を発見し、この走行車のスリップストリームに入るべく急加速を試みる事を追撃と称する。
アタックのチャンスとまったく逆であり、38km/hでしか走れない選手が40km/hの選手の後ろに入って走行している場合、ここから出てしまうと速度差でどんどん離されてしまう。前の選手は、後ろの選手を振り払うべくアタックを仕掛けるが、後ろの選手はこれから離されまいと追走を行なう。
 追撃とチャンス 追撃とチャンス
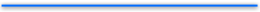
追撃はただ前の選手に食らい付く、追いつくだけでなく、その後にチャンスが発生する事もある。
例えば、前を走る選手がアタックをし、追いつくのに1分掛かるとする。この場合、ゴールまで1分より少し前の段階から追撃を開始すると、ゴール前数秒の所で、前を行く選手に追いつける事になる。
アタックをしかけた選手は、その分エネルギーを使って一時的に疲労し易い為、このタイミングで追い付く事が出来ると、前の選手は反撃が出来ないという場面がある。
前記のカウンターアタックのように、前の選手のアタックを追撃し、そのアタックを失敗させる事が出来ると、前の選手だけ特に疲れさせる事に成功する。こうなると、逆にこちらがアタックを仕掛ける絶好のチャンスとなる。
 追撃とタイム差 追撃とタイム差
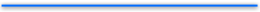
前方1kmほどに、同じ速度で走る集団がいるとする。この集団に入りたい場合、速度を上げて追いかける必要がある。
一度集団に合流できてしまえば、ドラフティングによって体力の消耗が落ちる為、いく分疲労を抱えても、速度を上げて追いかけた方がメリットが大きい。
むしろロードレースにおいては、この集団から取り残されてしまった場合、1人で追いかけ続けるのは不可能という事態に陥る危険性がある。
集団から切れてしまった場合、その離された距離が開けば開くほど、回復させるのが困難になる。まだ追いつけると決め込んで追いかけるのを後回しにすると、距離がどんどん拡大し、その追撃が大変困難になる。このような状態を、「傷口が広がる」と称する。
例ば、集団が50km/hで走り、切り離されてしまった選手は単独では45km/hまでしか持久出来ないとする。この場合、追いつけない。
しかしこの選手が、スプリントによって、55km/hまでなら10秒間維持できるとする。この場合、10秒間で縮める事ができる距離差は、13.8mである。つまり、これ以内の距離差であれば、この選手は集団に戻る事が出来るが、これ以上距離が開いた場合、この選手は追撃不可能となる。
そのため、たとえ疲れていても、13.8m以内に速度を上げて集団に合流しなければならない。当然前方との距離差は小さいほど直ぐに追いつけるから、早々に追いついたほうが結果的に疲れも少なくて済む。逆に今は疲れているからと追撃を後回しにすと、それだけ追撃に時間が掛かるため疲労し、更に13.8mより距離が拡大したら、その傷口は致命傷と化す。
また実際の所、追撃するとその後疲労するので、せっかく追いついてもまた離されたら意味が無いから、余力が残るタイミングとなると、更に距離は短くなるだろう。
この、前の集団や選手を捉える事が出来る距離やタイム差を、「射程範囲」といい、集団や選手を射程範囲に捉える事を、「射程圏内」と称する。射程圏内にいる、追撃する対象を決定する事を、「ロックオン」と称する事もある。
この、前の集団や走者に追いつくには、低速で時間を掛けて走るより、高速で短時間で追いついてしまった方が、負担が小さい。
例えば、前の選手と10m(車列5人分ほど)差が開いている場合、1km/hの速度アップでは追いつくのに1分も掛かる。これが2km/hであれば30秒であるが、短時間にスプリントを加え、5km/h程度加速すれば、12秒で直ぐに追走は完了する。一度上げた速度は惰性で暫く続く為、実際は半分の6秒程度のスプリントで、後はペダルを回さずとも自動的に到着する。
 数台のタイム差 数台のタイム差
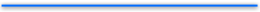
|
近距離計算用
|
|
距離差(1台=2m)
|
|
1台
|
2台
|
3台
|
4台
|
5台
|
速
度
差
(+) |
1km/h |
12秒
|
24秒
|
36秒
|
48秒
|
60秒
|
| 2km/h |
6秒
|
12秒
|
18秒
|
24秒
|
30秒
|
| 3km/h |
4秒
|
8秒
|
12秒
|
16秒
|
20秒
|
| 4km/h |
3秒
|
6秒
|
9秒
|
12秒
|
15秒
|
| 5km/h |
2.4秒
|
4.8秒
|
7.2秒
|
9.6秒
|
12秒
|
追走に掛かる時間を表にまとめた。この表は、目で見て台数で判断できる距離差(例えば5台分、10台分)で利用できる。
表の数値を暗記してしまうのが一番だが、計算し易い方法として、1km/hの列のみ暗記する方法を取り上げる。
まず、前の集団と自分の速度が同じである場合、速度を1km/h上げて追いかけると、1台につき12秒で追撃できる。
2台であれば×2、3台であれば×3で計算する。
その上で、速度差が2km/h(2倍)の場合は÷2、3km/h(3倍)の場合は÷3と計算する。
例えば、前に3台分程度差の開いた選手の後ろに入り込みたい場合、12×3台であるから36秒である。実際には+2km/hで追いかける場合、÷2として、18秒と割り出せる。
◆演算実習
各問題にて、B選手がA選手に追いつく(追いつくとは後ろに接近する事である)時間を演算しましょう。
問1、
A選手は40km/h、B選手は41km/hで追撃を試みる場合の追撃に掛かる時間は何秒か。
問2、
B選手の追撃速度を42km/hにした場合は何秒か。
問3、
A選手は40km/h、B選手は41km/hで追撃を試みる場合、掛かる時間は何秒か。
問4、
A選手は43km/h、B選手は47km/hで追撃を試みる場合、掛かる時間は何秒か。
問5
A選手が50km/hで逃げ、B選手が51km/hで追撃を試みる。この際、A選手がゴールラインを通過するのに残り1分であるとした場合、A選手は逃げ切れるであろうか。
問6、
A選手がゴール終盤に50km/hに速度を上げる事が出来るとし、B選手は52km/hで追撃が可能である。A選手がゴールラインを通過するのに残り1分である場合、B選手が先着する為には、最低でも残り何秒から速度を52km/hにしなければならないか。
※直ぐに答えられないと、レース中に使い物になりません。
⇒答え
問1=1台分は12秒、速度差1km/hの為、そのまま12秒
問2=速度差が2km/hの為、12÷2=6秒。
問3=12×3台=36秒。
問4=12×3台=36秒に加え、速度差4km/hのため、36÷4=9秒。
問5=12×5台=60秒=1分。ただし後ろに追いつくだけであり、車体1台分A選手が前にいるため、1車身差でA選手が先着。B選手の追撃失敗。
問6=5台差に加え、A選手を加えた6台×12秒=72秒。速度差2km/hの為、半分の36秒。36秒より早い時間からアタックを仕掛ければ追いつける。
いずれも複雑な計算式に見られてしまうが、ようは1台12秒を最小単位とし、台数分を掛け、速度で割るだけである。
 遠距離のタイム差 遠距離のタイム差
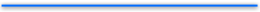
|
遠距離計算用(1分差)
|
|
|
30km/h
|
35km/h
|
40km/h
|
速
度
差
(+) |
1km/h |
30分
|
35分
|
40分
|
| 2km/h |
15分
|
17.5分
|
20分
|
| 3km/h |
10分
|
11.6分
|
13.2分
|
| 4km/h |
7.5分
|
8.75分
|
10分
|
| 5km/h |
6分
|
7分
|
8分
|
何台分の差か掴みにくい、より距離の開いた場合においては、上記の表を用いる。
上記グラフは、1分のタイム差がある場合、速度を上げる事で何分で追いつくことが出来るかをまとめた表である。
この表も一見複雑に感じるが、速度差+1km/hさえ理解してしまえば簡単に計算可能である。
逃げる対象より、速度を1km/h速く追いかけた場合、逃げる対象の速度が、そのまま分に変わるという特徴がある。
対象が30km/hで走っていれば30分、35km/hなら35分という具合である。
これを元に、+2km/hであれば1/2の15分に、+4km/hであれば1/4の7.5分と除算する。
更に、この数値は「1分差」の場合であるので、これに実際のタイム差分の倍数を掛ければ、追走に掛かる時間が判明する。
つまり、追いかけたい対象の速度をそのまま分に換算し、自分の追いかける速度差で割り、最後にタイム差を掛ける。
追撃時間=(逃げる対象の速度÷自分との速度差)×タイム差
◆演算実習
問1、
同じ30km/hで走るA選手が、ちょうど1分前に先にスタートした。この場合、自分の速度を1km/h速くして追いかけたら、何分後にA選手に追いつくか。
問2、
同じ30km/hで走るA選手が、5分前にスタートをした。自分の速度を1km/h速くして追いかけたら、何分後にA選手に追いつくか。
問3、
同じ30km/hで走るA選手が1分前にスタートをした。自分の速度を3km/h速くして追いかけた場合、何分後にA選手に追いつくか。
問4、
40km/hで走るA選手がタイム差3分で先行している。B選手が42km/hで追いかける場合、A選手に追いつくのは何分後か。
問5、
40km/hで走るA選手が、あと1時間(40km)でゴールに到着する。これを追いかける2分後ろを走るB選手は、最低でも何km/h以上に速度を上げなければならないか。
※直ぐに答えられないと、レース中に使い物になりません。
⇒答え
問1=30km/hを31km/hで追いかけると、30km/hがそのまま30分に変わる。
問2=5分前にスタートなので、30分×5=150(2時間30分)
問3=30km/h→30分。速度は3km/hなので÷3=10分
問4=40km/h→40分。タイム差3分なので×3=120分。速度差2km/hなので、÷2=60分。
問5=逆算の典型問題。40km/h=40分。2分差の為×2=80分。60分で追いつける速度を出す為、60÷80=0.75。これを40km/hに足して40.75km/h。
 タイム差の測定 タイム差の測定
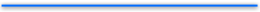
先行する選手が視界に入っていれば、その選手が通過した木や標識などを基準に、そこから時間を数え、自分がその基準値を通過した時間を測定する事でタイム差を調べる事ができる。
ただし、対象が視界に入らないほど離れている場合は判別不能である。この場合、見える範囲で最も遠い対象を基準にし、そこから時間を数えて、最低○○分以上と判断するしかない。
 追撃と持久力 追撃と持久力
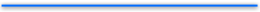
追撃をするには、先行する選手より速い速度を出す必要があるが、自身の出せる速度には限界がある。基本的に、速度を高くするほど、持続する時間が短くなる。
この項目は「持久力」の項目で詳細している。
そのため、いかに高速で走れても、追いつくまでに力尽きてしまっては、追撃が出来ない。例えばATP-CPの持久時間はおよそ8秒とされる為、8秒以内のタイム差であれば追撃出来るが、これを越えてしまった場合、追いつく前に失速してしまう。
このような場合、最低でもギリギリ持久しきれる速度まで落とさなければならない。このように、追撃対象まで距離差(やタイム差)が小さければ、より高速で短時間で追撃は完了出来るが、逆に差が大きいほど、より低速で長時間の追撃をするしかなくなる。
長時間であっても、低速で少しずつ追いつければよいように思うが、その間単独で追撃する場合、空気抵抗を受けながら長時間走行する事になってしまう。逆にいく分速度を上げたほうが早く集団に追いつき、追いついてしまえば空気抵抗が減って負担が小さくなる為、短時間に手早く追撃を完了した方が、トータルでの疲労は小さく出来る。
視界的に、直ぐ前に集団がいるからといっても、1km/h程度では追いつくのに中々の時間を要する。それが解糖閾など短時間しか持久できない速度に達していれば、余計に追撃に負担が掛かり、速度を見誤ると追撃する前に失速してしまう。
なおこれとは逆に、距離が接近すれば、その分速度を上げる事が出来る。最初は+1km/h程度でじわじわ追い上げながらも、解糖閾で走る射程圏内に入ったら、そこからは解糖閾で一気に+3km/hに速度を上げ、更に接近し、ATP-CPの射程圏内に入ったら、一気に+5km/hに速度を引き上げて追撃を短時間に完了する、という具合である。
|
近距離計算用
|
|
距離差(1台=2m)
|
|
1台
|
2台
|
3台
|
4台
|
5台
|
速
度
差
(+) |
1km/h |
12秒
|
24秒
|
36秒
|
48秒
|
60秒
|
| 2km/h |
6秒
|
12秒
|
18秒
|
24秒
|
30秒
|
| 3km/h |
4秒
|
8秒
|
12秒
|
16秒
|
20秒
|
| 4km/h |
3秒
|
6秒
|
9秒
|
12秒
|
15秒
|
| 5km/h |
2.4秒
|
4.8秒
|
7.2秒
|
9.6秒
|
12秒
|
この図は、近距離計算用の図を、出す事が出来る力で色分けしたものである。
赤=ATP-CPとし、10秒未満としている。
オレンジ=解糖閾の最高値とし、30秒未満としている。
また、解糖閾値では+3km/hまでしか出す事が出来ないとし、実現不可能な速度は灰色に塗っている。
例えば+5km/hの場合、台数4台までであればATP-CPの猛スプリントを仕掛ける事が出来るが、5台以上になると、途中で失速あるいは合流直後に失速する可能性がある事を示している。
5台以上の場合、解糖閾値に負荷を落とす必要があるが、解答閾値では+3km/hまでしか速度が出ない(灰色の部分)為、+5km/hで5台を追いかける事は出来ない。この場合+3km/hの20秒が最短時間となる。
|